File#4 家族・親戚関係について(原典分も補完)
やたらと登場人物の多い封神演義ですが、姫家や黄家などは特に一族のメンツが多いです。
ということで、このページでは特に家族が多い一族を図も用いてなるべくわかりやすく、漏れがないように解説してみます。二次創作の資料になれ
ば幸い。
(原典資料は光栄出版から出ている「完訳封神演義」を使用、以下光栄翻訳版と表記)
1 姫家
まずはなんといっても人数が多い姫家から。
奥さん20人以上、子供100人だからね!…と言っても、全員の名前が出たことはなく、登場できたのはごくごく一部。
歴史上の周王家の系図に関してはFile#2で触れたので、ここでは封神演義に登場しているキャラクターの血縁関係についてまとめます。
まずはフジリュー版から!
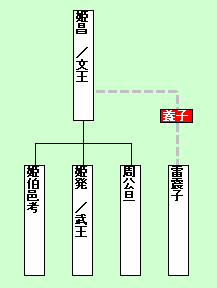
…人数多いよ!とか言っておきながら、漫画登場者は以下5人だけでした。
ちなみに邑姜の扱いですが、一応最終章で武王が彼女と結婚し、その息子が後を継いだということが「史実」として紹介されていますが、この物語の続
きが「史実」と同一かはわからないと書いていることから、あえて外しておきました。
しかし私は二人が夫婦になったことと信じてやまない。(WSの仙界伝弐では夫婦だったもんね!)
お次は光栄翻訳版に基づいた系図を。チラッとでも名前が出てきたら掲載・・・したら人数すごいことになった。
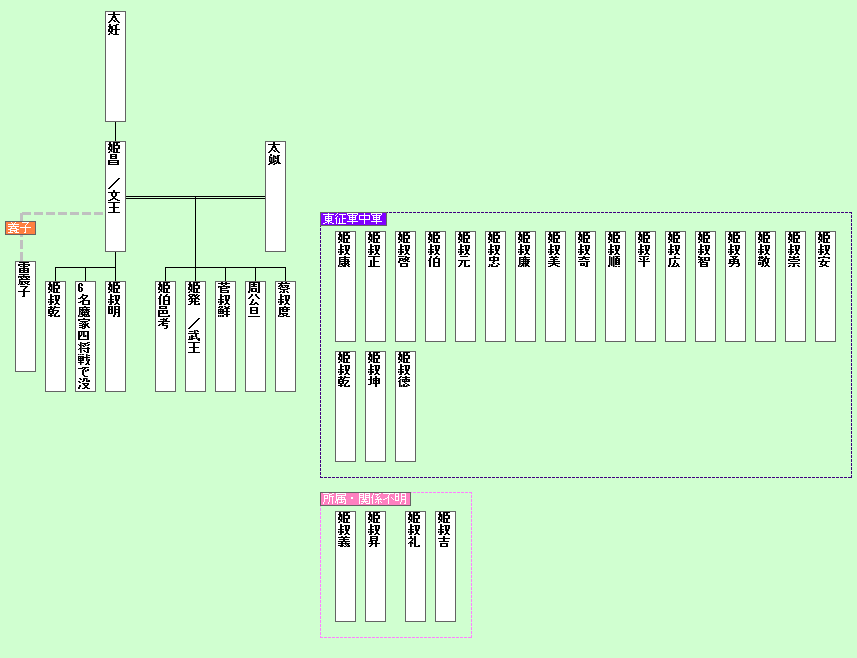
漫画で登場するキャラとFile2で紹介した人を除いて、それぞれを一応簡単に説明しておきます。
- 姫叔乾
- 姫家兄弟の中でたぶん一番最初の戦死者。姫昌の12番目の子。
黄家が西岐へ亡命した後、これを追いかけてきた風林に挑発されて出陣し、戦死した。
…でも光栄翻訳版ではなぜか東征軍編成時に名前が上がっている…別人?死んでなかったの?作者のミス?(安能版では姫叔建という名前が挙 がっている)
※彼以外にも、序盤戦で他6名が戦死している。(いずれも魔家四将戦・ただし安能版では姫家の出陣そのものがない) - 姫叔明
- 姫昌の72番目の子。
漫画版には未登場の武将・洪錦(元は截教(=漫画の金鰲島)の道士兼殷の将軍、帰順してなぜか竜吉公主と結婚する)に討ち取られる。 - 姫叔康、他
- 周軍が本格的に殷に進軍すると決めた際、姜子牙は軍を再編成して「東征軍」をつくって出陣しているが、
「東征軍中軍」にあげられている姫家の人々は皆その東征軍の中央軍(いわゆる本隊)に所属する将軍。
全員が姫昌の子かどうかは不明。
特に目立った活躍をしたものはいないけど、このうち下段に並んでいる武将は封神されている。
なお、安能版と光栄翻訳版とではメンバーの名前に若干の違いあり。(訳本の違いによるものか?)
姫叔乾→安能版だと姫叔建。安能版にも姫叔乾も登場するが風林戦で死亡・姫叔建も戦死。
姫叔元→安能版だと姫叔礼。光栄翻訳版でも姫叔礼は戦死者名として登場するが東征軍のメンバーではない。
姫叔美→安能版だと姫叔義。光栄翻訳版でも姫叔義は戦死者名として登場するが東征軍のメンバーではない。
姫叔奇→安能版だと姫叔昇。光栄翻訳版でも姫叔昇は戦死者名として登場するが東征軍のメンバーではない。 - 姫叔義・姫叔昇
- 張奎に奇襲されて封神。
- 姫叔礼・姫叔吉
- 時期は不明だがいつの間にか封神。魔家四将の犠牲者の一部か?
2 黄家
姫家の次に人数が多いんじゃないかと思われる黄家。フジリュー版で登場している人物は以下のようになります。
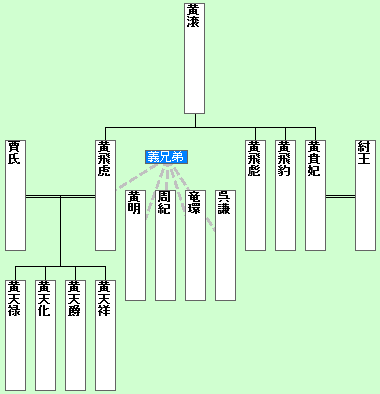
総勢10名+4名。
四大金剛もわかりにくいけど、飛虎の実弟なんてどっちがどっちかさっぱりわからなかったり。
光栄翻訳版では黄飛虎の義兄弟として鄧昆、黄滾の義兄弟に臨潼関の総兵・張鳳が加わるので、以下のようになります。
(天化の位置が次男から長男に変わってますが、原典では基本的に長男の扱いの模様。安能版は次男の扱いだけど何でだろ。)
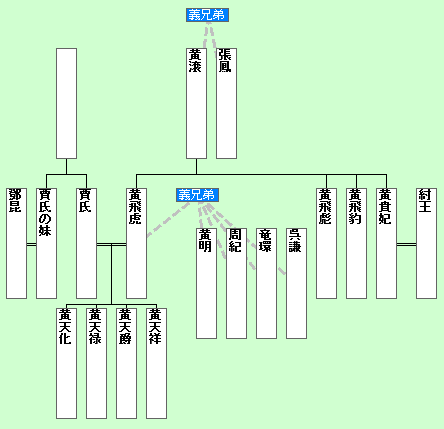
追加されている人のうち鄧昆だけ漫画未登場なので説明しておくと、賈氏さんの妹の旦那です。
そのことについてあまり知っている人はいなかったらしく、黄飛虎造反後も殷に残ってましたが、周が臨潼関まで迫った際、臨潼関への応援部隊と
して進軍し、そのまま周側に内応して味方に入ったという経緯あり。
ちなみにその後封神もされず、無事生き残った模様。
なお、フジリュー版では黄貴妃含む4名が封神されているわけですが、実は光栄翻訳版他原典だと生き残るのはさっき紹介した鄧昆以外では何とじ
いちゃんと孫の天爵のみ!(…天禄いつの間に死んだん?)
安能版では最後のシーンで天爵が「誰か一人でもいいから帰ってきてくれ!」と悲痛な声を上げていましたが、あまりの戦死率の高さにこちらも泣
きそうになります。
3 殷王家
フジリュー版での主要メンバーは少ないですが、主メンバー外や原典のメンバーも加えると膨大な数に膨れ上がります。まずはフジリュー版出演
メンバーのみから。(黄貴妃以外の妃の実家の血縁関係も一応入れてみた)
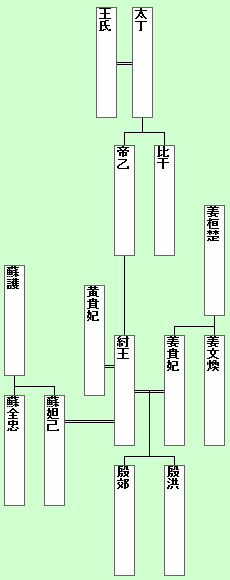
帝乙だけはマンガに登場してませんが、都合上入れました。
あと注釈が必要なのは太丁と比干かな。
太丁は1巻の物語冒頭で羌族狩りを命じた王氏(妲己)の旦那。遺体で1コマだけ登場。
比干も1コマ登場組だけど、こちらは聞仲が内政を任せると言った時に出た文官ブラザーズの1人。ブラザーズとか書いてるけど商容との兄弟関係
はないです。
さて、マンガ版はこの程度で済んでいますが、原典や安能版を含めた系図になると人数が更に増えます。
追加されたのは主に紂王の兄弟とか叔父とか、そのあたりですね。
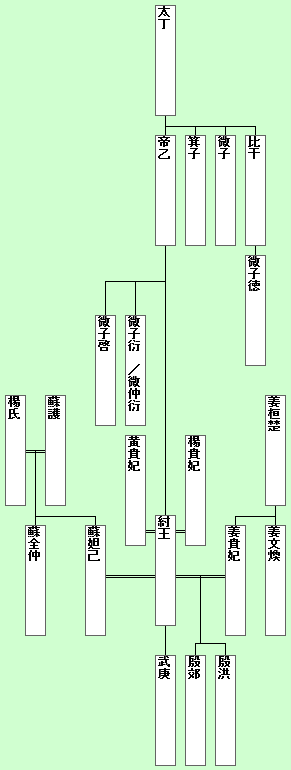
- 比干・微子徳
- 漫画にも登場しているが、目立った活躍をしていないためこちらで詳細記載。
比干は紂王の叔父に当たる人物だが、王家に忠実な臣下として、妲己に溺れる紂王を何度も諌め、時には妲己と敵対し、蠆盆に現れる狐(妲 己)狩りに協力したり、鹿台に現れた偽仙人(妖怪仙人)のあとをつけてそのアジトを武成王に頼んで焼き討ちしてもらったり、そのアジトに 隠れ住んでいた狐たちの毛を集めてコートを作って紂王に献上したりと、割と派手な活躍をする。
その為妲己に激しく恨まれ、喜媚と妲己の計略により自らの心臓を紂王に献上することとなり、封神された。妻と息子の微子徳がその後どう なったかは不明。 - 箕子
- 紂王の叔父。比干と同じく紂王をことあるたびに諌めていたが、聞き入れておらえず、逆に奴隷の身分に落と
された。賢人として有名だったらしく、革命後周王家に救出されたが、周の臣下となることを拒んだ。
封神本編の話ではないが、この後朝鮮半島へ逃げて「箕子朝鮮」という国を建国したとされている。しかし、この話は「源義経は密かに海へ出 てモンゴルに渡り、チンギス=ハーンとなった」という話と同程度の俗説とのこと。檀君神話との兼ね合い(檀君=韓国人が朝鮮国家の起源、 箕子朝鮮=中国人が朝鮮国家の起源)を考えると、少なくとも韓国側では支持されないと思う。 - 微子・微子啓・微子衍(微仲衍)
- 微子は紂王の叔父。他の二人ほど目立った動きをしていないが、箕子が奴隷として投獄された後、紂王の兄に 当たる二人の甥(微子啓と微子衍、微子衍については本来は微仲衍というのが正しい名前らしい?)を連れて殷を脱出した。
- 武庚
- File2の三監の乱に詳細有。
- 楊貴妃
- 唐のあの有名な玄宗皇帝の妃とは関係のない、同名別人。
東伯侯や武成王のような強力な後ろ盾がない妃で、黄貴妃と共に副皇后として後宮にいたが、姜貴妃が拷問され王太子兄弟が紂王に命を狙われ た際、黄貴妃に続いて二人を匿い、逃がす。しかし黄貴妃のように武家の出身でもない自分が、強力な後ろ盾のあった姜貴妃でさえ拷問を受け ているのに自分が逃れられるはずもない、と、直後に世を儚んで首をくくって自殺している。
4 その他の家
先にあげた3家ほどじゃないけど、他にも家族親戚総出演のおうちがいくつかあります。
李家のようにWJ版でも全員出ているものはいいとして、他に面白いところといえば鄧家(蝉玉の兄か弟で鄧秀という人物がいる)や、崇家(崇侯
虎の奥さんと息子のほか、崇黒虎にも奥さんと息子がいる)くらいかな。
でもあくまでも光栄翻訳版は光栄翻訳版、安能版は安能版、そしてWJ版はWJ版。そして妄想は妄想。混同してぐちゃぐちゃになるもよし、適当
に補完して一人うふふするもよし、何かのお役に立てれば幸いです。
参考文献
- 完訳 封神演義 上・中・下/許仲琳・編/光栄/1995年
- 封神演義/八木原一恵・訳/集英社/1999年
- 封神演義上・中・下/安能務・訳/講談社文庫/1988年
